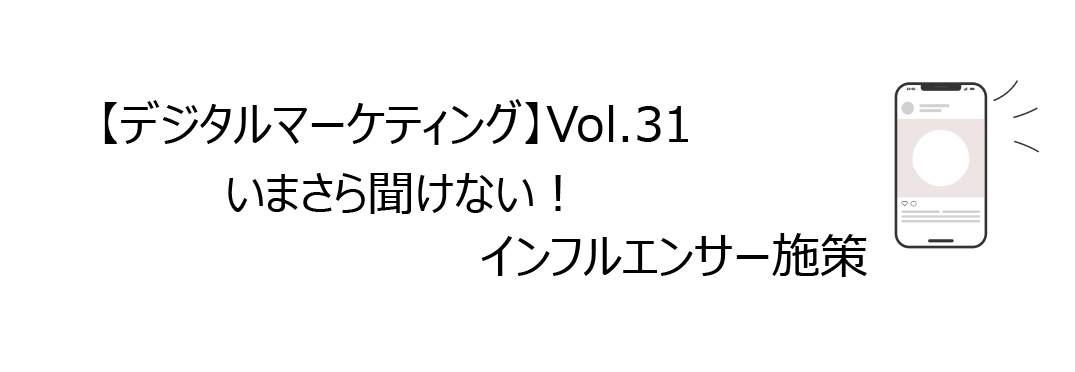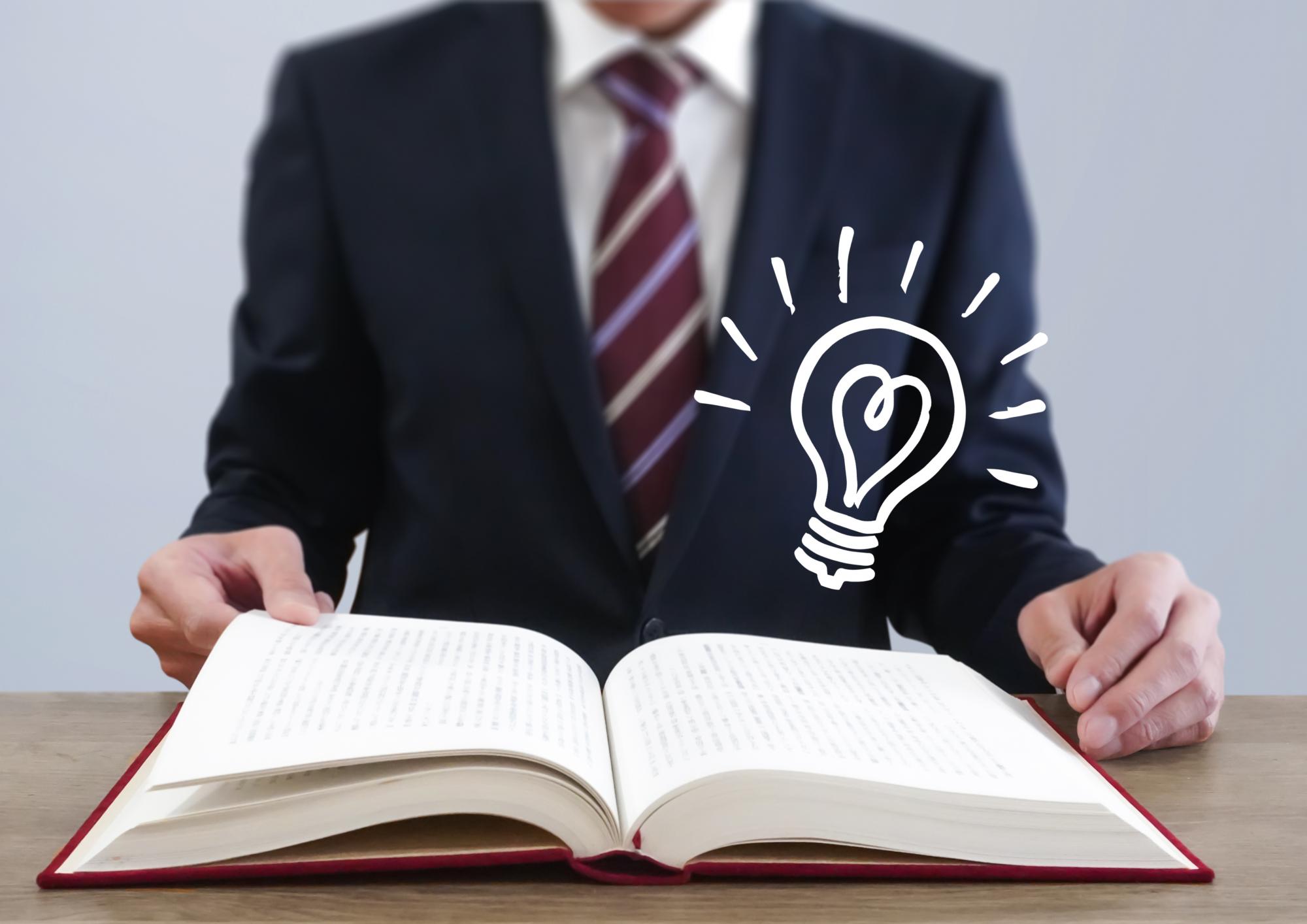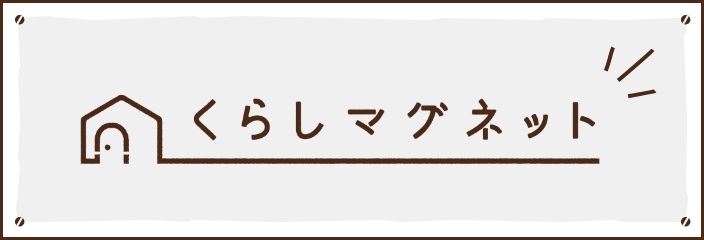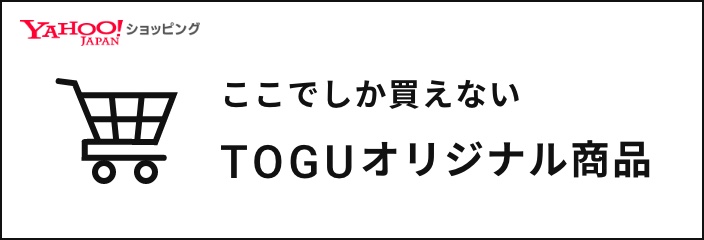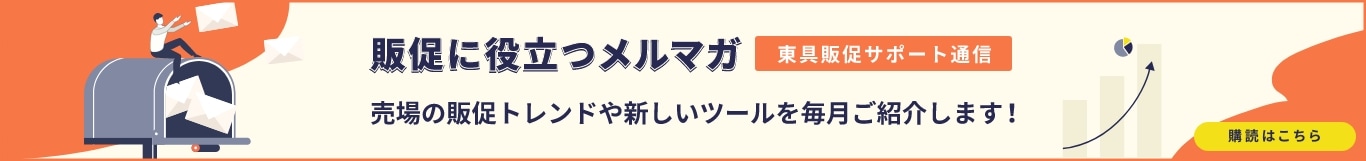2025.10.15社長コラム
未来に向けた投資
株式会社東具 代表取締役社長の清水貴義です。
日頃より、東具に関わる皆様方には誠に感謝いたします。
今年2025年の10月6日~13日までのノーベルウィークとして、ノーベル賞の授賞者が発表されました。
日本人では、大阪大学特任教授の坂口志文氏が生理学・医学賞、京都大学特別教授の北川進氏が科学賞を受賞されました。
これまでの国別の授賞者を自然科学系3分野(※文学賞・平和賞・経済学賞は除く)でみると、多い順から米国が285人、英国が89人、ドイツが73人、フランスが39人、次いで日本が27人と、実は日本は世界第5位という受賞者を生み出しているのです。
戦前はドイツが最も多く、英国、米国、フランスと続いて日本はゼロでしたが、直近の授賞者では日本は米国に次いで第2位でした。
米国やドイツに対して比ではない授賞者数ですが、世界の上位に位置していることは誇らしいことだと思います。
しかし、いま問題となっていることの1つに、研究費の少なさが挙げられています。
ドイツに比べて日本の研究費は3分の1ほどのようです。受賞者数がドイツは日本と比べて2.7倍になりますので、研究費の割合がそのまま影響しているようにも感じます。
また、ドイツの人口が約8,400万人、日本の人口が約1億2,300万人とされ、日本の方がドイツに比べて1.46倍人口が多いので、割合だけでいえばもう少し日本の授賞者が多くてもいいのではないかとも思います。
そして、2000年以降世界各国は大学の研究開発費を増やしています。ドイツは2.7倍、米国は3.4倍、韓国は7.0倍、中国に至っては35.9倍増。それに比べて日本は1.0倍と全く伸びていないのです。
研究費を出すのは主に大学ということになりますが、実際の問題としては長い基礎研究期間との兼ね合いなどもあり、なかなか満足する研究費は用意されないようです。
いくら能力やチャンスがあっても、研究に必要な費用が無いことで明るい未来が塞がれてしまうのは本当にもったいないことです。
企業においても、研究などといった企業のためになる投資は必要不可欠です。
国や国立大学とは違い、ある程度柔軟に投資自体はできますから、企業幹部はそれが必要かどうかをしっかり見極めて適切な投資をすることが大切だと思います。経費節減を過剰に考えて、いまやるべきことの判断を誤ってしまうこともあります。
そうならないために、現状を知って今後の予測をすること。個人の思い込みや思いだけではなく世界標準も見据えた考えをもつこと。 そして、その研究に携わる人の熱意を無駄に冷まし可能性を潰すことにならないよう、しっかりと相互理解を深めることに努めることが企業幹部の重要な役割だと私は思います。
日本は島国なゆえに、昔は自分たちの考えだけで満足していた部分がありましたが、いまこの時代においては、世界を見据えた思考をもつことと活動をしなければなりません。
いろいろな考えを尊重して、判断を誤らなければ明るい未来を築けると思います。