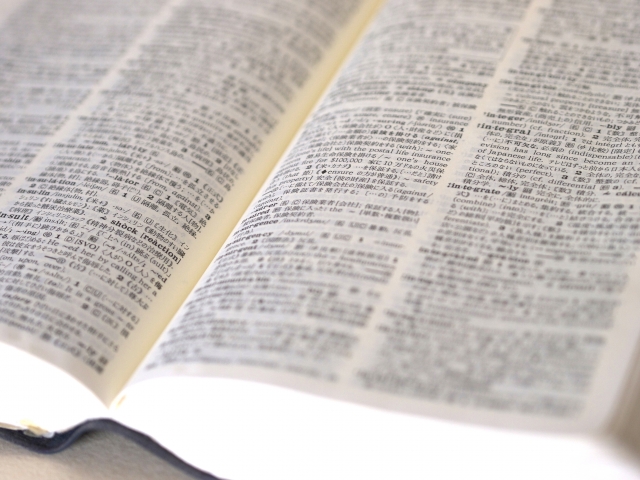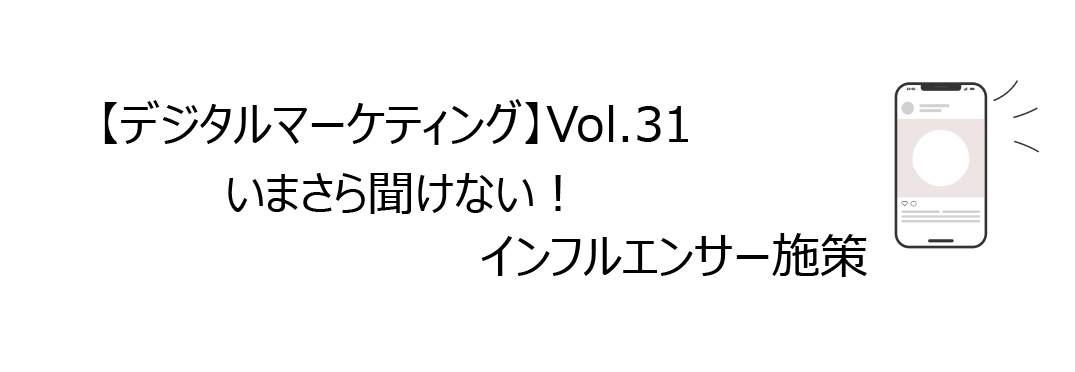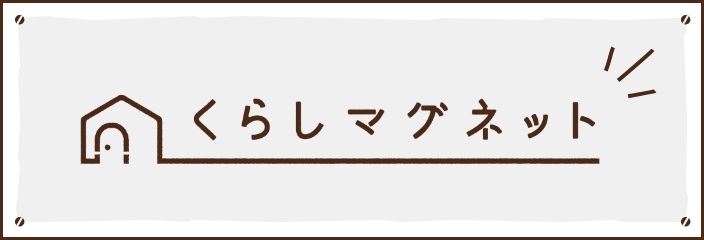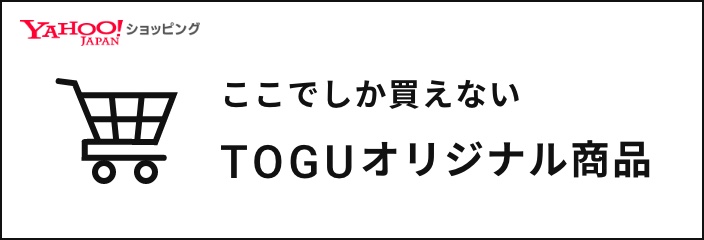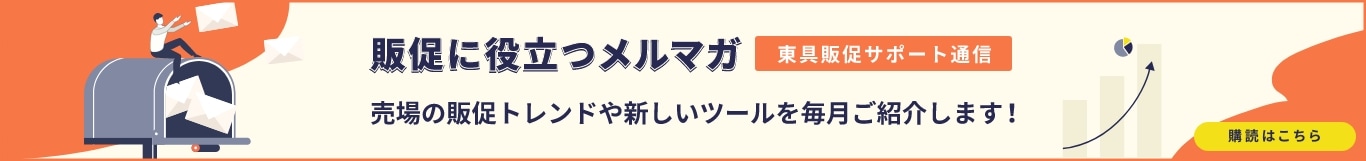2025.07.15仕事・スキル
注目を集める『ゼロパーティデータ』とは
こんにちは。大阪営業部の上田です。
今回は『ゼロパーティデータ』についてです。
デジタルマーケティングの進化に伴い、企業はこれまでにないほど多くの顧客データを活用できるようになりました。
しかし、近年では個人情報保護規制の強化や、サードパーティCookieの廃止といった潮流により、従来のデータ活用モデルは大きな転換点を迎えています。そんな中で注目を集めているのが「ゼロパーティデータ」です。
これは単なる代替手段ではなく、企業と顧客の信頼関係をベースにした、新たなマーケティングの形を象徴する考え方です。
ゼロパーティデータとは何か?
ゼロパーティデータとは、消費者が自らの意思で企業に提供するデータのことを指します。
これは、ユーザーの行動をトラッキングして得られるファーストパーティデータとは異なり、あくまで「自発的かつ能動的」に提供された情報です。
たとえば以下のようなケースが該当します。
- ユーザーが商品診断で回答した好みやニーズ
- 会員登録時に選んだ関心カテゴリ
- アンケートやフィードバックフォームでのコメント
- 「これから欲しい商品は?」という質問に対する答え
このようなデータは、顧客の意図や欲求が明確に表れているため、精度の高いパーソナライズ施策に直結します。
なぜ今ゼロパーティデータなのか?
ゼロパーティデータの重要性が高まっている背景には、以下の要因が挙げられます。
1. プライバシー規制の強化
欧州のGDPRや、カリフォルニア州のCCPAをはじめとするプライバシー法の拡大により、企業が第三者のデータを自由に活用する時代は終焉を迎えました。
AppleのiOSのトラッキング制限や、GoogleのChromeでのサードパーティCookie廃止の動きもあり、「取得元が不明なデータ」はリスク要因と見なされるようになっています。
2. 顧客のデータリテラシーの向上
ユーザー自身も「自分の情報がどう使われているか」に敏感になっています。
そのため、不透明なデータ収集や無関係な広告表示は嫌悪されやすく、逆に「自分が提供した情報に基づく体験」が歓迎されるようになりました。
3. 顧客体験(CX)の差別化
競合商品が溢れる現代において、購買体験そのものが差別化要因になります。
ゼロパーティデータを活用すれば、「このブランドは私のことを理解してくれている」という感覚を顧客に提供でき、ロイヤルティ向上に繋がります。
ゼロパーティデータを集める方法と工夫
ゼロパーティデータを効果的に集めるためには、ユーザーにとって意味のある「問いかけ」が必要です。ただ単に情報を要求するだけでは、顧客は協力してくれません。
そこで重要なのが、体験設計とインセンティブ設計です。
1. 診断コンテンツ
ファッションECでよく見られる「あなたに似合うアイテム診断」や、コスメブランドの「肌タイプ診断」などが好例です。顧客にとっては遊び感覚で参加でき、企業にとっては貴重な嗜好データが手に入ります。
2. クイズ・ゲーム形式
ポイント付与やクーポンをインセンティブとして提供する「クイズに答えてプレゼント」キャンペーンなども有効です。楽しく参加できる仕組みにすることで、データ提供の心理的ハードルを下げられます。
3. ウェルカムアンケート・登録フォーム
新規会員登録時に「どんな情報を希望するか」「関心のあるカテゴリは?」といった質問を設けることで、精度の高い初期セグメントが可能になります。
長くする必要はなく、2〜3問でも十分に価値があります。
4. チャットボットとの対話
AIチャットボットを使って、対話形式で情報収集を行う方法も効果的です。
顧客にとっては質問に答えているだけのように感じながら、実は企業にとってはゼロパーティデータが蓄積されていきます。
どのように活かすか?
ゼロパーティデータを収集した後は、それをどのように活用するかが鍵となります。
単にデータを集めるだけで終わってしまっては、効果は限定的です。
1.メールマーケティングのパーソナライズ
好みや購買意欲に基づいたメルマガの出し分けが可能に。たとえば「辛い料理が好き」と回答した顧客に対しては、スパイス系レシピや商品のレコメンドを行います。
2.レコメンドエンジンの強化
顧客の興味をベースにした商品提案ができるため、従来の閲覧履歴ベースの提案よりもクリック率やCVRが高まります。
3.CRM施策との連携
ゼロパーティデータをCRMに統合し、顧客ステージやLTVに応じたコミュニケーションを設計することで、効率的な顧客育成が可能になります。
課題と今後の展望
もちろん、ゼロパーティデータの活用にも課題は存在します。
一つは、「データの鮮度」を保つことです。顧客の嗜好や関心は時間と共に変化するため、継続的なアップデート機会を設ける工夫が求められます。
また、情報の取得方法によっては、「マーケティング目的が透けて見える」と顧客に不快感を与えてしまう可能性もあるため、誠実な設計と透明な説明が不可欠です。
今後は、ゼロパーティデータとAI技術の連携によって、より高度な予測モデルやパーソナライズが可能になると見られています。特に、ユーザーの入力情報と過去の行動を統合し、リアルタイムでニーズを先読みする「ハイブリッドCX」の実現が注目されています。
顧客の“声”を尊重するマーケティングへ
ゼロパーティデータは、企業にとっては高精度なマーケティングを実現する手段であると同時に、顧客にとっては「理解されている」という安心感を得られる体験の源泉です。
短期的な販促では得られない、持続的なブランド価値を築くための土台と言えるでしょう。
データ活用の未来は、技術ではなく信頼に基づいて進化していきます。
ゼロパーティデータはその中心にある、新たなマーケティングのスタンダードなのです。
私はゼロパーティデータの活用は、マーケティング手法の進化というよりも企業と消費者の信頼関係の構築の手段だと感じています。
私自身もよく使うサイトやアプリで積極的にアンケートに回答するようにしています。
自身の好みや関心に合わせた情報が提供される事は便利で快適ですし、不必要な広告表示や情報提供が少なくなる事にもメリットを感じるからです。
但し、回答はしたものの反映されていないと感じると提供元への不信感に繋がります。
提供元は聞いた事を活かす姿勢が必要であり、それが信頼に繋がるのだと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました。

google Geminiで生成